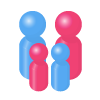遺言書作成
亡くなられた方が遺言書を残していない場合、その財産は全て相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合、その財産は相続人全員での法定相続分に基づく共有となります。
・配偶者に土地・家屋を残したい *1
・事業を継いでいる長男に会社の株を相続させたい *1
・相続人以外でお世話になっっている人にも財産を残したい
このような場合、相続人間での共有状態をもたらす法定相続では、必ずしも自分の希望する相続財産の承継を実現できません。
遺言書があれば、遺言が法定相続に優先し、上記のような自分の希望する相続財産の承継を実現できます。
≪*1 遺留分について≫
相続人には、遺言によっても奪うことのできない一定割合(法定相続分×1/2)の相続財産が留保
されており、これを「遺留分」といいます。遺留分を無視した遺言はそれ自体無効になることはあり
ませんが、後の「争族」を避けるためにも、遺言の際には留意すべき点です。
遺言には、原則として下記の3つの方式があります。(危急時を除く)
・自筆証書遺言
遺言者が作成要件に従い、全文を自署の上、作成する遺言方式です。
長 所
ⅰ.費用が掛からない
ⅱ.1人でいつでもどこでも書ける
ⅲ.公証役場への出頭・証人が不要
ⅳ.遺言の内容を秘密にできる
短 所
ⅰ.要式不備の為、遺言自体が無効となるおそれがある
ⅱ.遺言の紛失、隠匿、偽造のおそれがある
ⅲ.遺言の存在を相続人に気づかれない場合もある
ⅳ.遺言の有効性について争いになる場合もある
ⅴ.家庭裁判所での検認手続きが別途、必要
・公正証書遺言
公証役場において、証人(2人以上)立会の下、遺言者が公証人の面前で遺言内容を口授し、公証人が遺言内容を公正証書として作成する遺言方式です。
長 所
ⅰ.要式不備による遺言無効のおそれがない
ⅱ.公証役場にも遺言書が保管されるので、紛失、偽造等のおそれがない
ⅲ.公正証書である為、遺言の有効性についての争いが起こり難い
ⅳ.字を書くことが困難な場合でも可能
ⅴ.家庭裁判所での検認手続が不要
短 所
ⅰ.費用が掛かる(公証人、専門家手数料等)
ⅱ.遺言の内容が関係当事者には秘密にできない(但し、公証人・士業者には守秘義務有)
ⅲ.原則として公証役場へ出向かなければならない(但し、出張制度有 要 別途出張費)
・秘密証書遺言
遺言者が作成要件に従い、全文を作成(署名を除き、ワープロ等可)の上、当該遺言書を封入、封印し、公証役場において、証人(2人以上)立会の下、当該封書が遺言書であることを公証してもらう遺言方式です。*存在の公証であり、内容の公証では有りません。
長 所
ⅰ.署名を除き、自署する必要がない(ワープロで作った遺言書に署名だけ自署)
ⅱ.遺言内容を秘密にできる
ⅲ.封印されるので偽造等のおそれがない
短 所
ⅰ.要件不備の為、遺言自体が無効となるおそれ
ⅱ.費用が掛かる(公証人・専門家手数料等)
ⅲ.原則として公証役場へ出向かなければならない(但し、出張制度有 要 別途手数料)
ⅳ. 家庭裁判所での検認手続が別途、必要
≪付言事項について≫
法律上の効果(財産の承継先等)を発生させる遺言内容には厳格な要式性が求められます。
しかし、遺言書には、法律上の効果を伴わない、付言事項を記載することが可能です。
付言事項の例としては、配偶者、相続人への感謝の言葉であったり、なぜ、このような
遺言書を書いたのか(法定相続分とは異なる相続分の指定をした理由)等が挙げられます。
これらの文言があることにより、後の相続争いのリスクが軽減されるかもしれません。